
Google Appsの導入で先進のコラボとコストダウンを シングルサインオン環境を安価に構築 「繋吉(つなよし)」
GmailやGoogle Calender、Google DocsなどGoogleアプリケーション(Google Apps)の法人用アカウントの導入で、自社のITコストを10分の1ほどにまで圧縮でき、同時に生産性を向上できることをご存じだろうか。
強力なグループウェア機能、容量ほぼ無制限のメール機能とアンチスパム機能などによって、これまで「所有」していたIT資産をクラウドから利用できるようになる。そんなGoogle Appsの導入支援に加えて、既存システムとGoogle Appsへのログインを一度に実現するシングルサインオン環境を提供するのが、「繋吉(つなよし)」である。
シングルサインオンは、単にログインが1回で済むというだけではない。
社の生産性を高めるとともに、きめ細かなセキュリティの設定にによって、各ユーザーに何が許可され、何が禁止されているのかを明確に線引きすることによって、コンプライアンスを確保するものである。
吉積情報(株)が提供する「繋吉」は、Windows Serverの標準ディレクトリサービスである「アクティブディレクトリ」とGoogle Appsへのログインを一度で済ませるシングルサインオン環境構築ソリューションだ。
「繋吉」は各クライアントにインストールするだけでシングルサインオン環境が実現できる。専門的な知識がないユーザーの手でもインストールマニュアルを参考に、簡単にインストール設定ができるため導入費用はまったくかからない。経費も1ユーザー当たり年間1050円という破格の安さである。
また、その初期設定すらもすべてお任せしたい人には、Google Appsと「繋吉」の導入支援サービスも開始している。
「繋吉」はIPアドレスによってログインの可否を設定できるので、自社内端末とモバイル端末からのログインを許可し、インターネット喫茶からのログインは禁止するといったきめ細かな設定が可能だ。
その他オプション設定を行うことで、ユーザビリティを下げることなくセキュリティを高める事が可能なので、クラウド化によりどこからでもアクセス出来てしまう、と言う従来の欠点を補う事が出来る。
2009年の新型インフルエンザ・パンデミックにより、年内にも第2波の襲来が懸念されるが、万が一全社員自宅待機という事態になっても、モバイル端末さえ用意して「繋吉」を導入しておけば、業務が継続できる。
Google Appsの導入によって節減できる自社IT資産の代表的なものとして、メールシステム、グループウェアシステム、アンチスパムシステム、そして今や軛(くびき)となっているMicrosoft Office Systemが挙げられる。
Gmailの強力なスパム機能に加えて、容量ほぼ無制限でメールが保存できることの恩恵は極めて大きい。自社所有のメールシステムだと、容量制限によって古いメールは削除することを余儀なくされるが、Gmailでは何十年分ものメールを保存しておき、自由に検索することができる。
メール送受信記録には、貴重な業務ノウハウが詰まっている。ひとつの商談をまとめるのに交わしたメールにラベルを付しておくことによって、ひとつの「案件事例」が出来上がる。これは中途半端にナレッジマネジメントシステムを導入するより、はずかに実用的なナレッジとなり得るのだ。
そして、ITコストのかなりの部分を占めているMicrosoft Office Systemは、Google Docsの導入によってかなりの数を撤廃できる。
また、同一文書の複数ユーザーによる更新も、Microsoft Office Systemではその都度配布してバージョン管理を行わねばならないが、Google Docsならばブラウザ上からコラボしながらの更新が可能となる。
Google Calenderは、Ajaxと呼ばれるインタフェースにより、直感的に操作でき、社のメンバー全員の予定が一覧できるので、予定管理が極めてスムースに運ぶのである。
ITは、「所有する」時代から「利用する」時代へと移行しつつある。多額のリース料を払って導入しているグループウェアやMicrosoft Office SystemをGoogle Appsに移行することによって、機動力のあるIT基盤を構築することができる。
また、シングルサインオンのメリットを理解しながらも、初期コストがネックになって導入を見送っていた企業は、「繋吉」によるリーズナブルなシングルサインオン環境構築を検討してみる価値があるだろう。
■本件に関するお問い合わせ先
担当:柴田一人
TEL:03-5637-7407
FAX:03-5637-7407
E-mail:info@yoshidumi.com
(TechinsightJapan編集部 真田裕一)
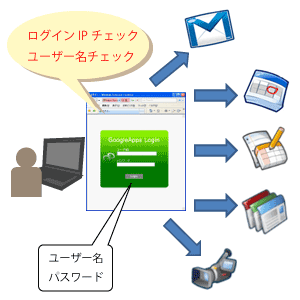
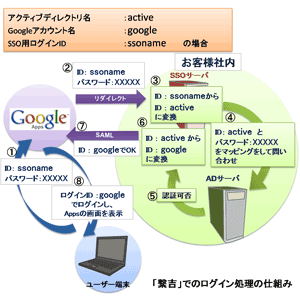
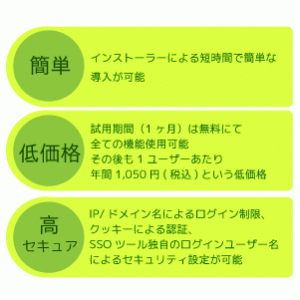



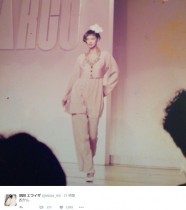





 <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
<